パニック障害とは
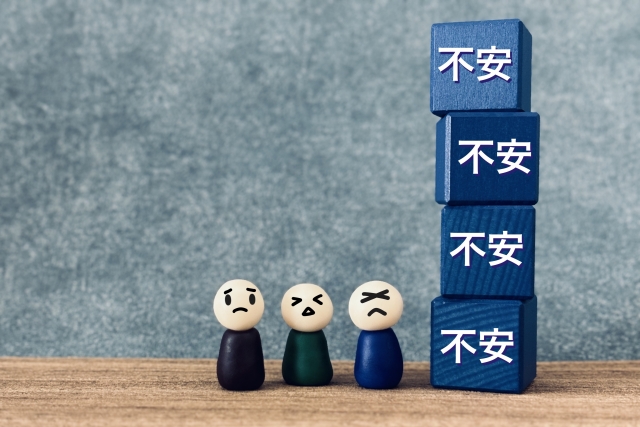
何の予兆もなく突然、動悸、息苦しさ、異常な汗、めまい、吐き気、手足の震えといった発作(パニック発作)が起きます。このパニック発作が起きると、死んでしまうのではないかと思い、さらなるパニックに陥ってしまいます。そのため、再度発作が起きたらどうしようかと不安になり、特に、外でパニック発作が出たらどうしようと考え、外出ができなくなってしまうことがあります。こうしてパニック障害は生活に支障をきたします。
「救急車で運ばれ、検査をしてもどこも異常ありません」
パニック発作は繰り返し起こるため、はじめは心配していた家族や友人も「またか」「気持ちの問題」と理解してくれません。
パニック発作は、人が危機的状況の時に現れる生命防衛反応が出てしまっているだけです。
事故や災害などに遭うと、人は身を守るために緊急事態であることを知らせます。
ところが何らかの原因でその反応が誤作動してしまってるだけです。
生命の危機に直面したような発作が何度も起きれば、「死んでしまう!」と思うのは当然です。
でも、安心してください、パニック障害の発作で死ぬことはありません。
予期不安
パニック発作を繰り返すうちに、「また発作が起きるのではないか」という不安を常に感じ、発作のない時も次の発作を恐れるようになります。「また起きるのではないか」「次はもっと激しい発作ではないか」「今度こそ死んでしまうのでは」といった不安が消えなくなります。これが「予期不安」で、パニック障害に多くみられる症状です。
広場恐怖
発作が起きた時、そこから逃れられないのではないか、助けが得られないのではないか、恥をかくのではないか、と思い、苦手な場所ができて、その場所や状況を避けるようになります。これを「広場恐怖」といいます。
苦手な場所は広場とは限りません。一人での外出、電車に乗る、エレベーターに乗るなど、人によって恐怖を感じる場所は様々です。広場恐怖が強くなると仕事や日常生活ができなくなり、また引きこもりがちになるので友達との人間関係にも影響が出てきます。一人で外出できなくなるので、人に頼っている自分自身を情けなく思う気持ちも強まっていきます。
パニック障害は珍しくありません
一生の間にパニック障害にかかる人の割合は1000人に6~9人と言われています。特に女性は男性よりもかかりやすい病気です。
パニック障害の治療
薬物療法と精神療法(認知行動療法)が中心
薬物療法と精神療法(認知行動療法)が中心になります。治療の目的には、「パニック発作を起こさない」ことが第一目標で、次いで「予期不安や広場恐怖もできるだけ軽減させる」ことが目標になります。
パニック障害は薬が効きやすい病気です
一般的に、最初に使われる薬はSSRI(選択的セロトニン再取込み阻害薬)をはじめとする抗うつ薬の一種です。また、安定剤(抗不安薬)もしばしば使われます。
これらの薬の効果は人によって違うため、効果を確認しながら増減したり薬を変更したりする必要があります。正しく効果を確認するためには、医師が定めたとおりの量と回数を守って服用してください。SSRIは副作用が少なく依存性が生じない反面、急に中止すると断薬症状としてパニック発作と似た症状(めまい、発汗、吐き気など)が出てしまうことに注意が必要です。安定剤は、即効性が期待できる反面、長く使い続けると依存性が生じてくることがあります。
パニック障害は薬物療法が効果を発揮しやすい障害です。「薬に頼らず気持ちだけで治す」というのは得策ではありません。
パニック障害・不安障害の方への私たちの支援
~精神的アプローチ~
パニック障害では、薬物治療に加えて精神療法の併用が重要です。とくに、曝露療法や認知行動療法は、薬による治療と同じくらいパニック障害に治療効果があることが認められています。薬が効き始めて発作が起こらなくなってきたら、苦手だった外出などに少しずつ挑戦していきます。
訪問看護ステーションこころいKでは、一緒に行動します。まずは玄関から出る、人のいない場所に行ってみる、駅の方にも行ってみる、電車に乗ってみる。看護師がついていますので万が一パニック発作がでても大丈夫です。無理をせずスモールステップで振り返りながら前進していきます。できることが続けば自信につながり、一人でも自由に外出することができます。





