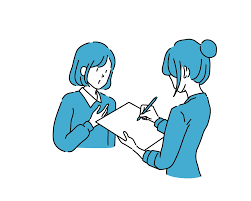認知行動療法とは

わたしたちは日常、物事を主観的に判断します。
しかし、その判断には人それぞれ癖があります。
例えばストレスを感じたりした時、悲観的に考えて落ち込み、それを引きずる人もいれば、すぐに立ち直る人もいます。
これは認知の違いから生じています。
学習の理論をもとに患者の行動の変容を促す「行動療法」と、医師が患者の認知の歪みを捉え、積極的にアドバイスをすることで治療の効果を期待した「認知療法」が基礎となっていますが、あくまでも現在行われている認知行動療法とは、認知と行動に働きかける技法の総称だと言えます。
うつ病や双極性障害、パニック障害、強迫性障害など、さまざまな精神疾患の治療にも有用とされ、近年日本でも注目されています。
また英語では、Cognitive Behavioral Therapyと表記され、CBTと呼ばれています。
認知と感情、行動の関係性について
同じ出来事でも人それぞれ認知の仕方や、生じる感情が違い、またその先の行動も異なります。
例えば、下記のような状況を例に挙げて、認知と感情、行動の関係を見てみましょう。
図の考え方だと、「上司とのコミュニケーションを避ける」というマイナスの結果になってしまいます。
しかし、もしここで「上司がメールを確認していないだけかもしれない」という別の認知をした場合、感情や行動も変化する可能性が高くなります。
つまり、出来事を「どう認知するか」で感情や行動が変わるため「認知」と「行動」、そして「感情」は密接に関係していると言えます。
認知の歪みが起こることで生じる、つらい感情や憂うつ感を軽減するために、認知や行動の変容を促すのが認知行動療法の基本的な考え方となります。
認知行動療法の流れ
①本人の問題となっていることの確認やアセスメント(情報収集・整理)
②本人の症状が起きるメカニズムなどについての心理教育
③治療目標の確認と、治療の実施
④記録やアセスメントに基づいた治療のステップアップや修正
⑤症状改善後の再発防止のためのカウンセリングなどの心理教育
治療の実施については、カウンセリングの面談だけではなく、活動を記録する、記入型のホームワークなどを取り入れて行います。
治療者用マニュアル
- うつ病の認知療法・認知行動療法 治療者用マニュアル
- 強迫性障害(強迫症)の認知行動療法 マニュアル (治療者用)
- 社交不安障害(社交不安症)の 認知行動療法マニュアル (治療者用)
- パニック障害(パニック症)の 認知行動療法マニュアル (治療者用)
- PTSD(心的外傷後ストレス障害)の認知行動療法マニュアル(治療者用)
効果
認知行動療法は、治療の効率性や効果の高さが世界中で評価されていると言われています。
具体的には、どのような効果が得られるのでしょうか?
回復率が高い
イギリスでの調査によると、「パニック障害」や「強迫性障害」における治療の約7割で、薬物治療よりも高い効果が示されたという結果が出ているそうです。
そのため、イギリスではどちらの疾患の場合でも、認知行動療法が治療法として選択されることが多いと言われています。
再発率が低い
追跡調査においても、薬物治療に比べ、認知行動療法は疾患の再発がしにくいという結果が出ています。
精神疾患は再発の可能性が高いものも少なくなく、その点からも、再発率が低いということは大きな効果であると言えるでしょう。
メリット
認知行動療法は、高く評価されている一方で、療法の性格ゆえに効果がある人もいれば、ない人もいる治療法です。
一般的には以下のようなメリット・デメリットがあると言われているので、参考にしてみてください。
メリット
- 副作用がない
- 薬物治療と同じような効果が得られる
- 治療だけではなく、予防的観点からも役立つ
デメリット
- 薬物治療と比較して即効性があるわけではなく、短期的に効果が出ない
- 一部の精神疾患には、まだ保険適用がされていない
- 認知行動療法の効果が出にくい、あるいはごくまれに、合わない場合もある
- 提供できる専門機関が少ない合わない場合もある
認知行動療法は、認知や行動に働きかけることで治療していくため、すぐに効果が出るわけではありません。
そのため、効果を得るためには長期的に取り組むことが重要です。