学校に行けなくても大丈夫!遊びを通じて育む対人スキル SSTと不登校支援
看護師 山田祥和
学校は「勉強するところ」だけではない
学校は国語や算数などの学習をする場であると同時に、人間関係を学ぶ重要な場所です。教室でのやり取りや休み時間の遊び、部活動を通じて、子どもたちは「挨拶」「順番を守る」「協力して何かを達成する」といった社会生活に必要なスキルを自然に身につけていきます。
しかし、学校に行がなくなるとこの人間関係を学ぶ機会が失われてしまいます。家庭学習やオンライン授業で勉強を続けることはできても、人と関わる練習の場は圧倒的に不足します。
結果として、人間関係がうまくいかなくなり、対人関係に自信を失い、ますます学校に行けなくなるという悪循環に陥ることも少なくありません。
人間関係は限定的になり、家族以外の人と接する機会が少なくなってきます。
こうした状況に対して、私たちは在宅でSST(ソーシャルスキルトレーニング)を行っています。

SST(ソーシャルスキルトレーニング)とは
SSTとは、人との関わりに必要なスキルを練習する心理社会的アプローチです。精神科医療や福祉の現場で幅広く使われていますが、児童への応用も非常に効果的です。基本的なSSTで扱うテーマには、
あいさつ
貸して」「ありがとう」「ごめんね」といった言葉の使い方
自分の気持ちの伝え方
順番を守る、ルールを守る
暗黙の社会のルール
天気などのたわいもない雑談
断り方、困った時の対処法
などなど。
これらは一見当たり前のようですが、不登校が続くと自然と学ぶ場がなくなり、社会生活に必要な力が徐々に弱まってしまうことがあります。
将来的には社会に出ていかなくてはなりません。どうしても辛くて学校に行けない場合もありますが、社会的に必要なスキルは学んでおきたいものです。
そこで、家庭という安心できる環境でこうしたスキルを身につける支援は非常に価値があります。
「遊びながら」の意味
SSTは単に座学のように教えるのではなく、「遊び」を取り入れることで効果が高まります。なぜなら、遊びには次のような力があるからです。
①楽しさによる動機づけ:勉強や練習と聞くと拒否的になる子どもも、「遊び」なら自然に参加できます。
②成功体験の積み重ね:「できた!」という達成感が自信につながります。
③人との関わりをポジティブに感じる:楽しい時間を共有することで、「人と一緒は怖くない」「むしろ楽しい」と思えるようになります。
例えば、
①カードゲームやボードゲーム(UNOやすごろく):順番を守る、勝ち負けを受け入れる
②簡単な工作やクッキング:役割分担、協力する体験、完成体験、喜びの共有。
③屋外遊び(状況に応じて):声をかける練習、チームワークを学ぶ。バドミントンなどで相手に気をつかうなど。
こうした活動を通じて、子どもは「人と関わる楽しさ」と「コミュニケーションスキル」を自然に学んでいきます。
訪問看護だからこそできる強み
不登校の子どもは、学校や学童など複数の人がいる場に強い不安を感じる場合があります。そうした場合、一対一という安心感、自宅という安全な環境で支援できる訪問看護は大きな意味があります。
また、訪問看護師は医療職であり、身体面・精神面の両方に配慮しながら関われるため、安心感を持って支援を進めることができます。加えて、子どもの状態や家庭環境をリアルタイムで観察できる点も大きなメリットです。
また、家族の話もゆっくりと聞くことができます。家族にゆとりができれば、子どもへの関わり方にも変化が生じます。
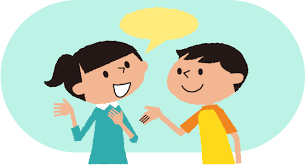
具体的な進め方
1. 目標設定(両親と支援者)
「挨拶ができる」「ありがとうが言える」など、小さな目標を明確にする。
2. 遊びを選ぶ(本人と支援者)
一番は本人がやりたい遊びを一緒に楽しむ。一緒に楽しみながら、挨拶やお礼、ルールなどのソーシャルスキルを学ぶ。年齢や興味に合わせ、簡単で達成感が得られる遊びが望ましい。
3. 振り返り(本人と支援者)
「ありがとうって言えたね」「順番を守れたね」と、できたことを言葉で伝え、自信を育てる。
4. 保護者への共有(両親と支援者)
家庭でも同じ言葉や対応を意識できるよう、保護者と情報共有する。
まとめ
学校に行けないことで学びの機会が止まってしまうのは、「勉強」だけではありません。「人と関わる力」を育てるためには、家庭でできる工夫が必要です。訪問看護は、そのサポートを行います。
「遊びながらSST」は、子どもが自然に、そして楽しく対人スキルを身につける方法です。訪問看護の新しい取り組みとして、この実践を広げていくことが、二次障害の予防にも繋がりますし、子どもたちの未来に大きな意味をもたらすと信じています。


