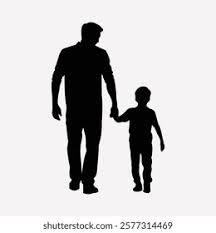不登校と発達障害の関係 「やる気がない」のではなく「やれない」
看護師 山田祥和
私が日々、学校に行けない子どもたちやその家族と向き合う中で、時々耳にする言葉があります。
「うちの子はやる気がないんです」という言葉です。当然そう思わないご家庭も多くありますが、どうしても「怠け」と捉えてしまうご家庭もあります。
実際、気合いと根性でうまくいったケースもありますが、私が子どとたちと関わると、その多くが「やりたいのにできない」「行きたいのに行けない」という強い葛藤を抱えていることが分かります。
特に発達障害の特性を持つ場合や不安障害(社交不安障害や強迫性障害)を抱えた場合、その背景はさらに複雑です。

不登校と発達障害は深く関係している
発達障害は生まれつきの脳の特性によるもので、本人の努力不足ではありません。代表的なものに、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などがあります。
学校は時間割通りに行動し、集団の中で協調しながら活動し、勉強するところ場所です。この環境は、発達障害のある子どもにとって多くのハードルを伴います。
例えばASDの子は予定変更や集団活動に強いストレスを感じやすく、ADHDの子は「分かっていても行動できない」ことがあります。LDの場合は特定の教科だけ極端に苦手で、努力しても成績が伸びないこともあります。
これらは意欲の有無ではなく、脳の情報処理の特徴によって起きる“やれない”状態です。
私も子どもの頃野球をしていましたが、私が寝食を忘れて、鬼気迫る、血が滲むような努力をしたとて、大谷翔平選手のようにはなれません。それと同じように、生まれ持っての脳の機能で、努力だけではどうにもならないこともあるのです。
支援現場で見える「やれない」のサイン
支援者として関わっていると、次のようなサインに出会います。
•朝の支度で一つの動作から次の動作に移れない
•授業中の雑音や光に耐えられず、頭痛や疲労を訴える
•友達とのやり取りで誤解が生じ、人間関係を避けるようになる
•課題の量やスピードについていけず、自信を失う
これらは外から見ると「やらない」「怠けている」に見えるかもしれませんが、実際は本気で頑張ってもできないことなのです。
「やらない」と「やれない」を区別する重要性
支援現場で一番避けたいのは、本人の“やれない”を“やらない”と誤解してしまうことです。
「頑張ればできるはず」と言われ続けると、本人は「自分はダメな人間だ」と感じ、自己肯定感が急激に下がります。この状態では学校に戻るどころか、日常生活への意欲さえ失われてしまいます。
私がいつも懸念している二次障害が生じる可能性もあります。
不登校が長期化する悪循環
支援者の立場から見ても、不登校は放っておくと悪循環に陥ります。
1. 学校での失敗や叱責が積み重なる
2. 自信を失い、登校への不安が増える
3. 朝になると体が動かない、行こうとすると吐き気や頭痛が出る
4. 周囲から「やる気がない」と誤解され、さらに傷つく
この悪循環を断ち切るには、本人の特性に合わせた支援が不可欠です。
支援者として実践している環境調整
日々の支援の中で、私が特に意識しているのは「環境を変えてやれる状態にする」ことです。
•小さな成功体験を作る:宿題を1ページだけやる、10分だけ教室に入るなど
•視覚的サポート:予定や手順を紙やホワイトボードで見える化
•感覚刺激の調整:静かな場所で学習できる環境を作る
•課題のカスタマイズ:量や難易度を本人に合うように調整
こうした配慮によって、子どもは「やれない」状態から少しずつ「やれる」状態へと移行していきます。

保護者との連携も鍵
支援者がどれだけ関わっても、家庭の理解と協力がなければ効果は半減します。保護者には「学校復帰が唯一のゴールではない」という考えを共有し、在宅学習やフリースクール、オンライン学習といった柔軟な選択肢を提案します。
また、家庭内での声かけも重要です。「どうして行かないの?」ではなく、「今日は何から始めようか?」という前向きな言葉に置き換えるだけでも、子どもの表情が変わることがあります。
「やれない」を「やれる」に変えるために
不登校と発達障害が関係する場合、必要なのは本人のやる気を引き出すことよりも、やれる環境を整えることです。私は本人が安心して挑戦できる場を作り、成功体験を積み重ねられるよう色々提案し、試行錯誤しています。
まとめ
日々の支援現場で強く感じるのは、「やる気がない」ように見える子どもの多くが、実は「やれない」状況にいるという事実です。
発達障害による特性と学校環境のミスマッチは、本人の努力では解消できません。周囲がその現実を理解し、環境を整えることで、少しずつ前へ進む力が戻ってきます。
私たち支援者の役割は、子どもが自分のペースで「やれること」を増やしていけるよう、根気強く伴走することだと思います。