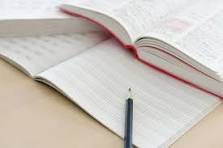精神疾患の予防 発達障害の二次障害を予防する② 二次障害を防ぐ!発達障害支援の7つの鍵
看護師 山田祥和
前回の記事です。
発達障害はその障害の特性からどうしても二次障害(例えば、うつ病や不安障害、依存症などの精神的な問題)を起こしやすいです。
じっとしてられない→怒られる
不注意→怒られる
片付けが苦手→怒られる
空気が読めない→孤独
共感性が乏しい→孤独
コミュニケーションが苦手→孤独
自信がなくなり、人との関わりも億劫になってきます。生きにくさを感じます。
するとうつ病や不安障害といった二次障害を引き起こす可能性があります。

当然、全員がそうではありません。周囲の理解があり、自己理解も進めば、二次障害を起こす可能性も減ります。
発達障害の支援で私たちが大切にしていることは、二次障害を予防することです。
私たちは予防するための支援方法として、以下のような関わりを行っています。
二次障害の予防
1.早期介入
早期に発達障害の診断を受けることで、サービスにつながります。早期の介入により、周囲の理解もすすみ、家族も孤立にくくなります。
2. 心理的サポート
発達障害を抱えていますとどうしても人間関係が上手くいかず孤立しやすいです。
私たちはよき理解者となり、よき相談相手になります。雑談などを通して
定期的に訪問することで、二次障害の兆候を早期に把握し、対処方法を提案します。
ご希望があれば認知行動療法(CBT)も行います。
3. 自己理解とストレス管理
自分の特性を理解し、ストレスや困難に対処するためのスキルを見つけることは予防において大切です。
自分の特性を紙に書き出し、ストレスが起こる出来事や、兆候、その時の対処方法を一緒に考えます。
強みを見つけ、自己肯定感を高めるためこともこらに含まれます。
4. 環境調整
学校や職場、家庭での環境を本人に合わせて調整することで、無理のない形で社会生活を送れるようにします。例えば、静かな場所での作業や、スケジュールの柔軟な管理ができる環境作りが有効です。
家族の正確な理解があれば本人のストレスは減ります。
5. ソーシャルスキルトレーニング(SST)
発達障害を持つ人が対人関係を円滑に築けるよう、ソーシャルスキルトレーニングを行うことが有効です。これにより、コミュニケーションの誤解やトラブルを減らし、対人ストレスを軽減できます。
6. 日常生活のサポート
生活のリズムを整え、適切な睡眠、食事、運動などをサポートすることも、二次障害の予防に効果的です。例えば、定期的な運動習慣やバランスの取れた食事が、心身の健康を維持するのに役立ちます。

7. 周囲の理解とサポート
家族や周囲の人々が発達障害に対する正しい理解を持ち、本人をサポートすることが重要です。家族や友人が協力し、過度なプレッシャーや誤解を避けることで、本人が安心して生活できる環境を作ることができます。
お子さんの場合ですとのびのび成長でき、人が嫌いにならず素直に育ちます。
これらの支援方法を組み合わせることで、発達障害のある人がストレスを感じずに生活でき、二次障害のリスクを減らすことが期待されます。
繰り返しますが、発達障害の二次障害は防げます。