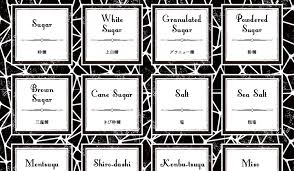精神疾患を抱えながら安定した日常生活を送るための工夫と習慣

看護師 山田祥和
精神疾患を抱えていると、本当に体調を崩しやすいです。こころの病気ですが、身体に不調をきたすのです。
日々の生活リズムや気持ちの安定が崩れやすくなり、ちょっとした出来事でも不安やストレスが強くなってしまうことがあります。
しかし、日常の中でできる小さな工夫を積み重ねることで、精神的な安定を得やすくなり、安心できる暮らしを築いていくことが可能な場合もあります。
ここでは、精神疾患と向き合いながら安定した生活を送るための、皆さん(当事者)が取り入れている習慣や工夫を紹介します。
1. 生活リズムを整えることが安定の第一歩
精神疾患のある方にとって、生活リズムの乱れは症状を悪化させる要因になりやすいと言われています。
規則正しい睡眠:毎日ほぼ同じ時間に寝起きすることを意識し、昼夜逆転や寝すぎを防ぐことが、気持ちの安定につながります。
昼夜逆転が精神状態を悪化させるのか、精神状態が悪いから昼夜逆転するのか、どちらが先か、、、しかし、規則正しい生活リズムは自分で意識することができます。
食事のリズム:朝食を摂ることで体内時計がリセットされ、日中の活動意欲も高まりやすくなります。栄養バランスを意識することも大切です。
適度な運動:ウォーキングやストレッチなどの軽い運動は、自律神経を整え、ストレスを発散する効果があります。
生活リズムは意外と手軽にできますので取り入れてみるといいと思います。
2. 感情を整える習慣を取り入れる
精神疾患を抱えていると、気分の浮き沈みや不安が強く出やすくなります。以下の習慣は気持ちを落ち着ける助けになります。
呼吸法や瞑想:1日5分でも深い呼吸を意識したり、静かに座って瞑想をすることで、心の緊張がほぐれます。
日記やジャーナリング:気持ちを文章にして書き出すと、頭の中の混乱を整理しやすくなります。
感謝リスト:その日にあった「よかったこと」を書き出すことで、前向きな視点を育てられます。
3. 人とのつながりを大切にする
孤独感は精神的な不安定さを強めてしまうことがあります。
信頼できる人との交流:家族や友人、支援者など、安心して話せる相手を持つことが心の支えになります。
専門機関や支援サービスの活用:地域活動支援センター、当事者会、相談員、デイケアや精神科訪問看護など、社会資源を利用することで孤立を防ぎ、安心感を得ることができます。
無理をしないコミュニケーション:大勢と関わる必要はありません。自分に合った範囲で人と関わることが大切です。
4. 環境を整えて安心できる暮らしを作る
心を落ち着けるためには、生活環境を整えることも重要です。
部屋の整理整頓:散らかった空間は気持ちの不安定さを助長します。少しずつ片づける習慣をつけましょう。
リラックスできる工夫:アロマや好きな音楽を取り入れることで、安心感を得られます。
デジタルデトックス:SNSやニュースを長時間見すぎると不安が増えることがあるため、利用時間を区切るとよいでしょう。

5. 自分を責めず、やさしく扱う
精神疾患を抱える人は、「できない自分」を責めてしまうことがあります。しかし、自己否定は症状の悪化につながることもあります。
完璧を求めすぎない:全部できなくても「少しできた」で十分です。
小さなご褒美を用意する:日々の中で達成できたことに対して、自分にご褒美を与えると前向きになれます。
休む勇気を持つ:「今日は休む」と決めることも、安定した生活のための大切な一歩です。
6. 専門家の支援を活用する
症状が強いときや不安が続くときには、専門家の支援を受けることが安定につながります。
定期的な通院:医師の診察を継続し、薬の調整や症状の確認を行いましょう。
デイケア:日中の安心できる居場所。専門スタッフによるケアで、心身の発達や社会性を育みます。症状についても相談できます。
カウンセリング:心の専門家との対話で、悩みやストレスを整理し、自分らしい解決策を見つける手助けになります。
精神科訪問看護:カウンセリングに近いですが、専門的な看護師が自宅に訪問し、症状の対処法や生活支援を行ってくれるサービスがあります。
相談支援事業所:福祉制度の利用や日常生活の相談に応じてもらえる窓口を活用することで、安心感が得られます。
まとめ
精神疾患を抱えながらも安定した日常生活を送るためには、生活リズムの安定、心を整える習慣、人とのつながり、安心できる環境づくり、自分へのやさしさ、専門家の支援が大切です。小さな工夫の積み重ねによって「自分らしい暮らし」を築いていくことができます。