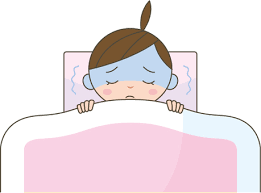わざと100点を取らない子どもたち 日本ならではの同調圧力
看護師 山田祥和
子どものテストの点数に注目する親は少なくありません。
「90点、95点、98点。惜しい! あと少しで100点なのに」
「見直しをすればきっと次は100点が取れるよ」
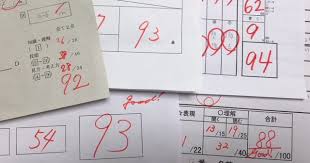
こうした声かけを繰り返しても、なぜか100点には届かない——。
そんな子どもがいたら、実はわざと100点を取らないという選択をしているのかもしれません。
その背景にあるのは、日本特有の“空気を読む文化”による同調圧力があるのかもしれません。
「飛び出た存在だと思われたくない」という思いから、あえて完璧を避ける。
これは、単なる努力不足や集中力の問題ではなく、集団の中で生きる術としての“自己防衛”なのでしょう。
「目立つことは危険」という無意識の学習
日本社会では、目立つことはしばしば警戒されます。とくに学校という小さな社会では、「浮いている子」や「できすぎる子」が標的になりやすい傾向があります。
子どもはその空気を敏感に感じ取り、無意識のうちに「突出しないこと=安全」と学びます。
100点を取ることで「すごいね!」と褒められる一方で、周囲から「ずる賢い」「調子に乗ってる」といった反応を受けた経験があると、次からは無意識に100点を避けるようになります。
「ダメだった」で、共感が得られるのです。
完璧を避けることが、仲間と平穏にやっていくための戦略になるのです。
空気を読むという名の“無言の圧力”
日本の学校では、「和を乱さない」「協調する」ことが美徳とされています。
その結果、空気を読む力は子どもたちの中で自然と育ちます。
しかし、この“空気を読む力”が過剰になると、子どもたちは本来の力を出すことにブレーキをかけるようになります。
点数をわざと下げたり、意見を言わなかったり、自分を抑え込むことで「みんなと一緒」の枠に自分を当てはめようとするのです。
そしてそれが繰り返されるうちに、「本気を出すこと」や「努力して突出すること」に罪悪感を覚えるようになります。
能力の高い子どもほど、自分の力を封印するという矛盾を抱え込むのです。
わざと100点を取らない理由の内側
では、子どもたちはどのような気持ちから“わざと”100点を取らないという行動に出るのでしょうか。そこには以下のような心理があります。
「優等生すぎる」と思われたくない
100点を取ったとき、「真面目すぎ」「ずるい」とからかわれた経験があると、成功体験すら嫌な記憶になってしまいます。
「目立ちたくない、みんなと一緒にいたい」
100点を取ることで周囲と差ができることを恐れ、「仲間でいたい」という強い承認欲求が行動を抑制します。
「嫉妬されたくない」「嫌われたくない」
周囲の目を気にしすぎることで、自分の行動を制限してしまいます。特に敏感な子ほどこの傾向が強くなります。
「空気を読んで合わせること」が正解だと思っている
成績だけでなく、行動や発言も“周囲と同じ”であることが安心材料となってしまい、本来の自分を出しにくくなります。

空気を読みすぎることの問題点
空気を読むこと自体は、集団生活を円滑にする上で必要なスキルです。
しかし、それが過剰になると、「自分を消す」ことにつながる危険性があります。
本音を言わない
本来の能力を発揮しない
他人に合わせてばかりで自分がわからなくなる
このような状態が続けば、自己肯定感は育たず、自信を持てなくなってしまいます。
やがて、「どうせ本気を出しても浮くだけ」「頑張っても無意味」と考えるようになり、挑戦を避けるようになることもあるのです。
また、思春期以降、「空気を読むことに疲れた」「自分の価値がわからない」といったアイデンティティの混乱や自己否定につながるリスクも無視できません。
「目立たないこと」が優しさであり、生きる知恵でもある
もちろん、こうした行動は子どもなりの知恵でもあります。
過剰に目立つことで孤立したり、傷ついたりした経験を避けようとしているのです。
ある意味で、わざと100点を取らないことは“空気を読む”高度な社会的適応行動とも言えます。
しかしその一方で、「目立っても受け入れられる社会」でなければ、子どもたちはのびのびと力を発揮することができません。
おわりに
わざと100点を取らない子どもたちは、「努力しても嫌われるかもしれない」「できすぎると怖い目にあう」と感じています。
それはまさに、日本社会の中で育ったからこその“知恵”でもあり、“葛藤”でもあります。
子どもの成績に一喜一憂する前に、その背景にある「空気」や「人間関係」に目を向けてみることが、今、求められているのかもしれません。