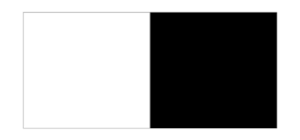メンクリに筋肉マンはいない? 筋トレをするから心が強いのか、心が強いから筋トレをするのか
看護師 山田祥和
メンタルクリニックの外来で、筋肉トレを習慣にしているような体つきの人はあまり見かけません。
筋トレをしているからメンタルを病まないのか、それともメンタルを病んでいないから筋トレができるのか?
本日はメンタルと筋トレの、鶏と卵の関係について考えていきたいと思います。
「筋トレはメンタルに効く」という言葉の裏側
SNSを見ていても、「筋トレすればメンタルが安定する」「筋トレはうつに効く」そんな言葉をよく目にします。確かに、筋トレはメンタルケアに効果的です。
ストレスが減り、自信がつき、睡眠の質が上がる。科学的にも証明されていることです。
しかし、こうした言葉を見て「自分は筋トレを始める気力もない」と落ち込む人もいます。
心が疲れているときほど、体を動かすことが難しいのも現実です。
筋トレをしている人は本当に「心が強い」のでしょうか?
それとも、「心が安定しているから筋トレできる」のでしょうか?

筋トレが心に良い理由
筋トレが心に良い理由を調べてみました。メンタルに良い影響を与えるのは、単なる気分転換や自己満足ではありません。
体の内側、つまり脳とホルモンの働きが変化するからです。
1. セロトニン・ドーパミン・エンドルフィンの分泌
これらの脳内物質は、幸福感ややる気、集中力を生み出す神経伝達物質です。
運動をするとこれらが活発になり、自然と「前向き」な気分になりやすくなります。
メンタルクリニックの外来で、黒々と日焼けしたスポーツマンはあまり見かけません。
2. 自己効力感(できる感)の向上
筋トレを趣味にしている人は言います。「筋肉は裏切らない」「やった分だけ成果が見える」
また、「昨日より重いものを持てた」「フォームが良くなった」この小さな成功体験が、“自分にもできる”という自信を育てます。
3. 生活リズムが整う
運動をすると睡眠の質が上がり、日中の覚醒度も高まります。
不眠や昼夜逆転を改善しやすくなることは、多くの精神科臨床でも確認されています。
つまり、筋トレは心を強くする科学的根拠のある習慣なのです。
それでも「筋トレができない心の状態」がある
一方で、心が疲れている人ほど、筋トレを始めるのは難しいものです。
うつ病や不安障害の方に「運動が大事」と伝えても、「やりたいけど動けない」と答えるケースが多いのが現状です。
筋トレを始めるには、意志や意欲や習慣など、心の基盤が必要です。
つまり、「筋トレをしている人」は、すでにある程度その基盤が整っている場合が多いのです。
筋トレできる=もともとメンタルが安定している
という側面があるのです。
だからこそ、筋トレができないからといって自分を責める必要はありません。
「まだ少し疲れているんだ」と受け止めることが大切です。
鶏が先か、卵が先か
では、結局どちらが先なのでしょうか。
「筋トレをするから心が強くなる」のか、それとも「心が強いから筋トレができる」のか。
答えは、その両方だと思います。
筋トレを続けることで、少しずつ心が安定していく一方で、心がある程度安定していないと、筋トレを続けることは難しいです。
つまり、筋トレとメンタルはお互いを支え合う関係なのです。
筋トレがメンタルを鍛え、安定したメンタルが筋トレを続けさせる。この循環が生まれると、人は自然に「心も体も強くなる」方向に進みます。

小さな一歩から始める「心の筋トレ」
心が疲れている人に、いきなり「ジムに行け」とは言えません。
でも、“少し動く”だけでも意味があります。
・朝に窓を開けて深呼吸する
・5分だけ散歩する
・寝る前にストレッチをする
・スクワットを3回だけする
これらも立派な「筋トレ」です。
体を動かすことができたという実感が、「自分は何もできない」という思考を少しずつ壊してくれます。
筋トレは“心の筋肉”を育てる練習でもあるのです。
動けない日があってもいい
筋トレをしていても、心が沈む日や動けない日は誰にでもあります。
大切なのは「続けること」ではなく、「また動きたい」と思える自分を責めないことです。
筋トレは、自分と向き合う時間。そして、心の中に“変わりたい”という気持ちが生まれたとき、その一歩を後押ししてくれるものです。
心が元気な人にも、少し疲れている人にも、筋トレはきっと味方になってくれます。
まずは今から少しだけ始めてしまうのが得策です。
私もこの記事を書いて、今スクワットを3回しました。