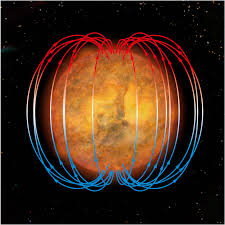「頑張れ」と言われるつらさ 〜うつ病の人が本当に欲しい言葉とは〜
看護師 山田祥和
はじめに
うつ病の人に対して、多くの人が励まそうとして「頑張れ」と思ってしまいます。
しかし、この「頑張れ」という言葉は、うつ病の人にとって大きなプレッシャーとなり、心をさらに追い込んでしまうことがあります。
そのことは、今では言っては行けない言葉と広く認識されていますが。
本記事では、なぜ「頑張れ」がつらいのか、その背景を解説するとともに、うつ病の人が本当に欲しい言葉や関わり方について、うつ病を回復した人に聞きましたので紹介します。

「頑張れ」がつらい理由
1. すでに限界まで頑張っている
うつ病の人は「怠けている」のではなく、心身が限界に近い状態で日常生活を送っています。
そのため、「頑張れ」と言われると「これ以上、どう頑張ればいいのか」と感じ、無力感や自分はダメだと自己否定につながることがあります。
2. 自分の苦しみが理解されていないと感じる
「頑張れ」という言葉の裏には、「今のあなたは努力が足りない」というニュアンスが含まれているように受け取られがちです。
その結果、本人は「理解してもらえない」「孤独だ」と感じ、心の距離が広がってしまうことがあります。
3. 「普通」に戻らなければならないプレッシャー
うつ病の人は「周りに迷惑をかけている」という思いを持ちやすい傾向にあります。そこに「頑張れ」が加わることで、「早く普通に戻らなければ」というプレッシャーが強まり、回復を妨げてしまうのです。
本当に欲しい言葉とは?
では、「頑張れ」の代わりにどのような言葉をかけると良いのでしょうか。ポイントは「評価や指示」ではなく、「共感と受容」です。
うつ病が良くなった利用者さんに、つらい時どんな声掛けをして欲しかっかたか聞きました。
1. 「無理しなくていいよ」
「無理をしているのでは」と心配している気持ちを伝える言葉です。安心感を与え、肩の荷を下ろすきっかけになります。
2. 「そばにいるからね」
孤独感をやわらげる一言。具体的なアクションがなくても、「一人じゃない」と感じられることは大きな支えになります。
3.「頑張らなくてもいいよ」
すでに十分頑張っていますのでわかってもらえたという気持ちになります。
4. 「大変だったね」「しんどいよね」
本人の苦しみをそのまま受け止める共感の言葉です。問題を解決する必要はなく、気持ちを認めてもらうこと自体が安心につながります。
5. 「休んでいいんだよ」
うつ病の人は「休むこと」に罪悪感を抱きがちです。そのため、休むことを肯定されると安心して療養に専念できます。
もちろん上記の言葉が誰にでも当てはまるわけではありません。相手との関係性や状態、その人の性格にもよります。ただ一つ言えることは責め立ててはいけないということです。
言葉以外のサポートも大切
声かけだけでなく、さりげないサポートも効果的です。例えば以下のような関わり方があります。
一緒に静かな時間を過ごす(ただ隣に座っているだけでもよい)
食事や日常のサポートをさりげなく行う(買い物や料理など)
病院やカウンセリングに付き添う
気分転換の促しはいい時と逆にプレッシャーになる時がありますので、様子を伺いながらになります。
大切なのは「相手を変えようとしない」こと。状況を無理に改善しようとせず、安心して過ごせる環境を一緒に整えることが支えになります。

家族や周囲が意識したいこと
1. 励ましよりも寄り添いを
「頑張れ」という励ましは控え、共感的な言葉を心がけましょう。
2. 回復には時間がかかると理解する
うつ病は風邪のようにすぐ治る病気ではありません。焦らず長期的な視点で支える姿勢が大切です。
3. 自分も無理をしない
支える側も疲れをため込まないように注意しましょう。サポートする家族自身のケアも欠かせません。
まとめ
「頑張れ」という言葉は善意から出てくるものですが、うつ病の人にとっては逆に負担になってしまうことがあります。
代わりに「無理しなくていいよ」「そばにいるからね」といった共感的な言葉や態度が、本人にとって大きな支えになります。
うつ病は一人で抱えるには大きすぎる病気です。支える側のちょっとした言葉や態度が、回復への大きな力になることを忘れずに、寄り添っていくことが大切だと思っています。
私も長いこと精神科の地域支援をしていますが、うつがひどい時は特にこれと言って何もしていません。
つらい気持ちに共感しつつ「何なとかやり過ごしましょう」と伝えています。