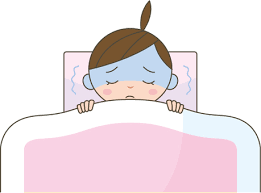発達障害 文献を参考に家族の関わり方を考えてみた 「普通じゃなくていい」と思えるように
看護師 山田祥和
発達障害のあるご家族との関わり方について、多くのご家族が日々悩み、模索しています。発達障害とは自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)など、さまざまな特性を含みます。
ご本人も困難を抱えていますが、実はご家族もまた、大きな負担やストレスを抱えがちです。今回は、発達障害のあるご家族との関わり方を、文献を参考にして、実践的な視点から紹介していきます。

理解が最初の一歩
まず、最も重要なのは「理解」です。発達障害は決してわがままやしつけの問題ではなく、脳の特性によるものであり、ご本人自身が最も困難を感じていることが多いのです。
宮内ら(2012)の文献レビューによれば、発達障害児を持つ家族は、特に母親が高いストレスを感じやすく、継続的な包括支援が必要と指摘されています。周囲の理解が得られにくいために、孤立や不安を抱えてしまうことも少なくありません。
育て方が悪いなどと言われて、辛い思いをしたという話はよく聞きます。
受容することの大切さ
次に大切なのが、「受容」です。「普通になってほしい」「周りと同じように」という期待や圧力が、かえって本人を苦しめ、家族関係を悪化させることがあります。
Olsson & Hwang(2001)の研究では、家族の精神的健康には「家族レジリエンス(家族の強み、復元力)」を引き出し、本人の特性をそのまま受け入れる姿勢が重要とされています。
「障害を個性と捉えて受容する」ということです。
環境を整える
では、実際にどのように関わればよいでしょうか。最も実践的なのは、「環境調整」です。発達障害の特性として、感覚過敏や変化への対応が難しいことがあります。スケジュールを視覚的に明示したり、ルーティン化した生活を整えることで、本人の安心感が高まります。
具体的には、「ちゃんとして」ではなく、「イスに座って」と明確な指示をする、「今日は何をするか」を絵や文字で示すなどの工夫が効果的です。
1週間の行動予定も立てたりすると有効です。見通しがつかないと不安になってきますので、先が見える関わりがいいです。
肯定的な関わりで自信を育てる
また、「肯定的な関わり」を増やすことも大切です。発達障害のある方は、日常生活の中で失敗や叱られる経験が多くなりがちであり、自己肯定感が低下してしまうことがよくあります。
小さな成功体験を積み重ね、本人が自信を持てるようにサポートしていきます。
米国で行われたWashington‑Norteyら(2025)の研究では、親が子どもに対して現実的でポジティブな期待を持つことが、本人の成長や家庭内の安定に大きく寄与すると示されています。

家族自身もサポートを受ける
一方で、ご家族自身が疲れてしまわないことも重要です。家族支援の文献レビュー(宮内ら, 2012)によると、発達障害のある子どもを育てる家族が孤立しないためのピアサポートや相談機関の利用が、ストレス軽減に非常に有効です。
定期的な家族会への参加、地域の支援センターや相談機関への相談を積極的に行うことが、家族全体の心理的負担の軽減につながります。
将来を見据えた準備
最後に、「将来への視点」を持つことも忘れてはいけません。発達障害のあるご本人とその家族は、就労や自立など将来に対する不安を抱えがちです。
早期から就労支援施設や福祉制度を理解し、準備していくことで、家族が安心感を得られ、本人も自信を持って将来を考えることができます。
発達障害のある家族との関わりは決して簡単ではありませんが、理解、受容、環境調整、肯定的関わり、そして支援を活用しながら進めていけば、家族がより良い生活を送ることは可能です。家族だけで抱え込まず、地域や専門機関との協力を通して、共に歩んでいく姿勢が何より大切です。
家族と共に歩む支援のかたち
困難もありますが、それ以上に「可能性」や「成長」があります。大切なのは、家族だけで背負わないこと。そして、「理解しようとする姿勢」こそが、支援の出発点です。
発達障害は目に見えづらく、他者から理解されにくいものです。しかし、少しの工夫や支援によって、本人の生活はぐっと安定し、家族関係も改善します。家庭内での安心感が、その人の生きる力につながります。
地域には、家族会、福祉サービス、医療機関など、多くの支援があります。どうか、孤立せずに、勇気を持ってつながりを持ってください。
そして、本人が「自分らしく生きられること」、家族が「笑顔でいられること」こそが、支援の最終的なゴールだと考えています。