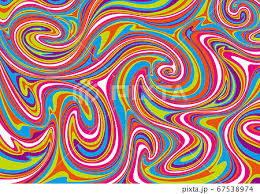双極症(双極性障害)には低め安定がいいのか? 不調と感じていても実は普通の可能性も?
看護師 山田祥和
双極症の治療において、よく「低め安定」を目指すと言います。一般的に双極症において「低め安定」はいい状態とされています。
「低め安定」とは?
「元気すぎず、落ち込みすぎず」、ややテンションが低めでも安定して生活できている状態を指します。いるんだか、いないんだかわからないくらい存在感がなく、静かな状態です。

なぜ「低め安定」が良いのか?
1. 躁状態のリスクを避けやすい
躁状態は本人にとって快感を伴うこともありますが、その後の反動でうつ状態に急落することが多く、そのうつ状態が長く続くこともあります。
低めに保つことでハイテンションになりすぎることを防ぎやすく、反動によるうつ状態も予防できます。
2. 生活の継続性が保てる
躁状態になると人間関係が壊れることも、経済状態が破綻することもあります。躁を抑えることで生活が安定します。
仕事・家事・対人関係など日常生活のリズムが保ちやすくなり、再発防止にもつながります。
躁のあの感覚を知っていると、確かにつまらないかもしれませんが、長い目で見たら生活は確実に安定します。
3. 長続きする
躁の時は疲れ知らずで、寝ないで活動します。頭も回り、何でもできると思い、やりたいことが次々に浮かびます。
またそれができてしまいます。しかし、長続きしません。元気すぎると活動しすぎて疲れがたまり、反動でうつになることもあります。
「低め安定」なら体力的・精神的にも長続きします。
「低め安定」はうつ状態ではない
低め安定の特徴
食欲・睡眠:まずまず、保たれている
意欲:そこそこある(最低限の活動は可能)
希死念慮:ない、あっても強くない
疲労感:少なめ・コントロール可能
身体症状 : ない、または強くない
社会生活:何とか維持できる(通院・家事・仕事など可能)
▼うつ状態の特徴
食欲・睡眠:乱れがち(過眠・不眠、食欲低下または過食)
意欲:かなり低下(何もやる気が起きない)
希死念慮:あることがある(自殺を考えることも)
疲労感:強く感じる(朝からだるい、何をしても疲れる)
身体症状 : 頭痛、腰痛、息苦しさ、下痢、便秘
社会生活:維持困難(外出困難、人との接触を避ける)

普通の状態を「低い」と感じがち
当の本人は、低いと辛いです。「低め安定」は安定とは捉えにくいです。
躁状態である調子が高い状態を、良い状態である感じてしまうと、普通の状態であっても調子が悪いと感じてしまいます。
それだけ躁状態は万能感みたいなものが生じます。あの感覚が忘れられないからかもしれませんが、一度躁を経験してしまうと、実は普通の状態でも本調子ではないと感じるのかもしれません。
実は「低い」のではなく、「普通の状態」なのかもしれません。主観と客観の違いですね。
まとめ
双極症(双極性障害)では「低め安定」が長期的にみても安全で、再発を防ぎやすい状態です。
実は、調子が良くないと感じていても、普通の状態の可能性もあります。
多少テンションが低く感じても、それで穏やかに暮らせるなら十分に良好な状態です。
気分の波を「ゼロにする」のではなく、「大きな振れ幅を避けて穏やかに保つ」ことが目標です。