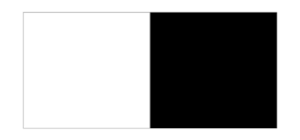双極症(双極性障害)の仕事選びについて考える 波の中でも働き続けるために
看護師 山田祥和
うつではない時や軽い躁の時は、マルチタスクがこなせ、創造的な仕事もでき、集中力も持続します。ハードワークもこなせ、仕事を任せられることも多いと思います。
しかし、一度うつに転じてしまうと頭が回らなくなり、体調も不安定になって今までできていた仕事ができなくなってしまうことがあります。仕事を辞めざるを得ない状況に陥る場合もあります。
というわけで、本日は双極症の仕事について考えていきます。
最初に結論から言いますと、私が思う仕事を長く続けるポイントとしては、以下の4つです。
①双極症の「波」は性格ではなく病気の特徴
②仕事選びは“うつ期でも続けられる”を基準に
③「得意なとき」と「つらいとき」両方の自分を想定して選ぶ
④自分の波を理解し、調整できる働き方を見つける

1. 双極症における“仕事の難しさ”
うつではない時には集中力・発想力・行動力があり、どんな仕事でもこなせます。
一方で、うつ期になると頭も体も動かず、人に会うのもつらくなります。
この「波の差」が、仕事の継続を難しくしています。
しかし、これは怠けではなく病気の特性です。決して能力がないのではなく、病気がそうさせているのです。
まずは、自分はダメだと思わず病気を受け入れることからです。
「また訪れるであろううつ期を」
そこから仕事を「安定して続ける」ための工夫が必要になります。
2. 仕事を選ぶときに大切な3つの視点
当然人にもよりますが、うつ時でも、体が覚えていて、ルーティンな、人とあまり関わらない仕事だと、案外と何とかなる場合もあります。
① うつ期でも耐えられるか
うつ期には、思考力も体力も落ち込みます。
その時期に“最低限こなせる仕事”かどうかが重要です。
単純・定型作業(データ入力、軽作業など)
自分のペースで進められる仕事
在宅や短時間勤務など、柔軟な環境
「うつの時でも何とか続けられるか」を基準に選ぶのがポイントです。
② 人との関わりの少なさ
人間関係のストレスは、双極症の再発要因になりやすいものです。
人との距離を自分でコントロールできる仕事が向いています。
在宅ワーク(文章作成、データ処理、翻訳など)
プログラミング・デザインなどの技術職
図書館・倉庫・清掃などの静かな職場環境
③ 好調期の力を「活かせる余地」があるか
うつ期に合わせるだけでは、退屈になりやすい人もいます。
軽躁期の集中力や発想力を発揮できる場があると、仕事にやりがいを感じやすくなります。
クリエイティブ系(デザイン、文章、企画など)
短期集中型の業務(プロジェクトベース、スポット案件)
「波の上の時」を活かせる仕組みを持つと、自己肯定感を保ちやすくなります。

3. 働き方をデザインするという考え方
双極症の仕事選びでは、「職種」だけでなく「働き方の柔軟さ」がカギになります。
たとえば――
週3勤務+在宅中心
フリーランスとしてペースを調整
企業に属しつつ業務量を相談しながら進める
年金+単発バイトで無理をしない生活
大切なのは、自分の波を前提とした設計をすることです。
「体調に合わせて仕事を変動させる」発想を持つと、長く安定して働けます。
4. 自分の波を知ることが、仕事選びの第一歩
仕事を選ぶ前に、自分の調子の変化を把握しておくことも大切です。
アプリや手帳で「気分・睡眠・集中度」を記録していくと、「朝に弱い」「3日続けると疲れる」などの傾向が見えてきます。
そのデータをもとに、「自分は短時間集中型」「週末に落ち込みやすい」などの特徴を踏まえて仕事を選ぶと、無理のないマッチングができます。
上手に波を乗りこなしている人をみていると、自分の状態を何かに(スマホやメモ帳)書き表している人が多いですね。
5. 波の中でも働ける環境をつくる
双極症の人にとって、仕事選びは「波の理解」と「調整力」になると思います。
調子のいいときの自分を基準にするより、うつ期の自分でも守れるペースを大切にすることが、長期的な安定につながります。
波があるからこそ、創造力や共感力も深まります。
双極症を“欠点”ではなく“個性”として受け止めながら、自分のリズムに合った働き方を見つけていくことを私はお勧めします。
うつ期をなんとか乗り越えようともがくよりも、何となくやり過ごすくらいの気持ちの方がいいですね。