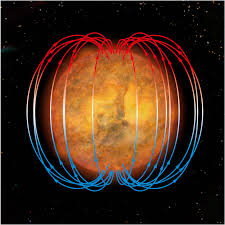精神科訪問看護で使えるちょっとした技術 ラベリング効果
看護師 山田祥和
精神科訪問看護の現場では、服薬管理や体調確認だけでなく、利用者さんとの関わりそのものが大切な支援になります。特に「言葉の選び方」は、利用者さんの気分や行動に大きな影響を与えることがあります。
その中で活用できる心理学的手法が「ラベリング効果」です。
ここでは、ラベリング効果の基本から、精神科訪問看護における具体的な場面事例、実践のポイントまで紹介します。

ラベリング効果とは?
ラベリング効果とは、他者から与えられた評価や言葉が、その人の行動や自己認識に影響を及ぼす心理現象です。
例えば「優しい人ですね」と言われ続けると、「自分は優しい人でいなければ」と無意識に考え、実際の行動も優しさに沿ったものになっていきます。逆に「怒りっぽい人だ」と言われ続けると、そのラベルに合わせて行動してしまうこともあります。
つまり、周囲がどんな言葉を投げかけるかで、その人の行動は大きく変わるのです。
訪問看護の現場でよくある場面
事例1:気難しい利用者さんに「穏やかですね」と声かけをする
ある男性利用者さんは、普段から苛立ちやすく、訪問中に怒鳴ってしまうこともあります。ちょっとしたことが気になり、ご近所さんとのトラブルもあります。
看護師はあえて怒りには触れず、落ち着いている場面を見逃さずに、
「○○さんは、普段とても穏やかに話してくださいますよね」
「寛大ですね」
「落ち着いて話してくれるので安心できます」
と声をかけ続けます。すると徐々に本人も「自分は穏やかでいなければ」という意識を持つようになり、苛立ちは減っていきます。
事例2:飽きぽい中学生の利用者さんに「粘り強いね」と声かけを続ける。
習い事も長続きせず、すぐにやめてしまう男子中学生。頑張り屋になってもらいたいですので、
「粘り強いねー」
「努力できるね!」
「頑張ってるね」
と嫌味にならないように声かけをしていきます。すると自分は頑張り屋で努力家であるという認識が生じます。
事例3:ある女性利用者さんは、家族との関係が希薄で「私は誰からも必要とされていない」と話しています。
看護師は、ささいな配慮に注目し、
「気遣ってくださって本当に優しいですね」
「そういうところが素敵です」
と伝えることを続けます。本人は最初は否定的でしたが、繰り返し伝えるうちに「私、少しは優しいところがあるのかもしれない」と受け入れ、自己肯定感が高まっていきます。
事例4:行動を促すために「先に感謝する」
ゴミ出しや洗濯などの日常生活動作を嫌がる利用者さんには、「やってくれてありがとう」を先に伝える方法が有効です。
実際に、ある訪問で「今日はゴミ出しをお願いしてもいいですか?」と声をかける前に、
「○○さんがいつもやってくださるから助かります。本当にありがとうございます」
と伝えると、本人は「やってないのにありがとうって言われた」と笑いながらも、その後自然にゴミ出しを行いました。
これはラベリング効果に加えて「先取り感謝」の心理効果で、本人が「ありがとう」に応えようとする気持ちが働いた事例です。

精神科訪問看護における実践ポイント
1. ポジティブなラベルを選ぶ
「怒らないで」ではなく「いつも穏やかですね」。否定形ではなく、肯定的な言葉を選ぶことが重要です。
2. 繰り返しが大切
一度だけでは効果は薄いため、毎回の訪問で意識的に伝えることがポイントです。
3. 行動の前に感謝を伝える
「ありがとう」を先に言うことで、そのラベルに沿った行動を引き出しやすくなります。
4. 無理をさせない範囲で
本人が受け入れやすい言葉を選び、過度な期待やプレッシャーを与えないことも大切です。
5. 本人が少しでも頑張っているところを認める
あまり頑張っていないことを認められても、嬉しくありません。ちょっとでも意識している部分を認めるだけで、その行動は強化されます。
まとめ
精神科訪問看護では、薬の管理や体調確認だけでなく、言葉かけの工夫そのものが支援になります。ラベリング効果を活用することで、利用者さんは自然にポジティブな行動を取るようになり、関係性も安定しやすくなります。
「いつも穏やかですね」
「優しいですね」
「ありがとうございます」
この小さな言葉が、利用者さんの生活を前向きに変えるきっかけとなります。